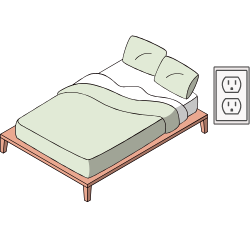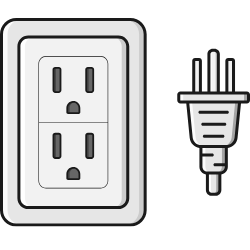水害にそなえて
今回は、今からできる水害対策の準備をご紹介します。
1.土のう・水のう
土のうとは、布袋に土砂を詰めたものです。
これを積みあげて、水や土砂の流れを止め、
家屋への浸水を防止するので、
水深の浅い初期段階や小規模な水害時には、非常に有効な対策です。
低地に住んでいる方は、常備しておくのが賢明ですが、
袋いっぱいの土を集めるのは、特に土の少ない都会ではなかなか大変です。
そういった場合には、40~45リットルのゴミ袋を2~3枚重ね、
水を入れて作る「水のう」も有効です。
水のうを複数個用意し、段ボールに詰めることで土のう代わりにもなります。
水害被害を受けやすい半地下・地下に玄関や駐車場、居室があるお家に
お住まいであれば、土のうは常に準備しておくのが良いです。

2.止水板
大雨時には、家の出入り口に、長めの板などを設置し、
土のうや水のうなどで固定して、浸水を防ぎましょう。
板がない緊急の場合は、
テーブル・ボード・タンス・ロッカー・畳などで代用しても良いです。
なお、止水板を購入に対して補助金を出してくれる自治体もありますので、
お住まいの自治体のHPなどをチェックしてみましょう。
3.排水溝のチェック
ゲリラ豪雨など、突発的で激しい水害時は、
トイレや浴室、さらには洗濯機などの排水溝から汚水が逆流する
「排水溝逆流浸水」が発生し、室内から泥水が噴き出す恐れがあります。
水のうを1階のトイレの便器に入れる、浴室、浴槽、洗濯機の排水溝の
上に乗せる、といった対応で逆流を防止しましょう。
4.自作のハザードマップ
自治体の作成したハザードマップは非常に重要なものですが、
それに加え自前のハザードマップを用意しておくことも大切です。
水害が起きて、避難が必要になった時のために、
避難場所までのマンホールや小川、側溝などの危険箇所を
マップ上に示しておくと良いです。
特に濁流で冠水した場合、危険箇所が見えなくなり、避難途中でふたの外れた
マンホールや側溝に落ちてしまうことも非常に多くあります。
通常の降雨時に避難場所まで歩いてみて、自作のハザードマップに、
雨が降った時の水の流れる方向やマンホール・側溝の場所の目印に
なるものも書き込んでおきましょう。